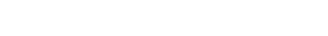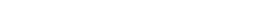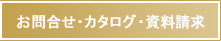たくみアカデミーインターンシップ報告会
みなさんこんにちは!新築・改築・リフォーム・リノベーションあなたのこだわりお聞かせください。
村瀬建築㈱ 施工部の渡邊です。
先日たくみアカデミーにて、総合実習発表会とインターンシップ報告会に参加してきました!
その中のインターンシップ報告会で、昨年インターンシップの受け入れをした生徒さんから、村瀬建築で学んだことや感じたことを、1対1の対面で報告してもらいました。

インターンシップ報告会の様子
パワーポイントを使ったプレゼン資料を準備してくれていて、インターンシップを通して感じたことをわかりやすく伝えてくれました。
村瀬建築での実習を通して、自分に足りないものに気づけたり、社長の話を受けて、今までの目標より一段高い目標を設定し努力していきたいと思うようにたったことを伝えてくれたことが印象的で、少ない期間のインターンシップでしたが、自分の糧になるものがあったことを嬉しく感じました。

昨年のインターンシップの様子(CADを使った設計)

昨年のインターンシップの様子(現場地盤調査の立会い)
報告してくれた生徒さんはこの春から2年生になり、就活や資格取得、日々の学習などより充実した一年になると思います。
今回報告してくれた自分の思いを大切に、また実行しながら、これから過ごしていってほしいなと思います。
応援しています。
村瀬建築では、より良い住まいとなりますよう、ぎふ県産材ヒノキや無垢材を使用した新築、改築、リフォームやリノベーション、古民家リノベーション、耐震診断・耐震リフォームなどの災害対策、手刻み大工の家づくりなど様々な暮らしづくりのお力になります。お気軽にご相談ください!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
公共工事をする事について
皆様こんにちは、社長の村瀬です。
今回は公共工事についてお伝えさせていただきます。
村瀬建築㈱は民間工事だけではなく、公共工事も施工しております。
主な受注先は岐阜市や岐阜県、岐阜県警、厚生労働省、法務省で、年間に2、3件を請け負っています。
公共工事を施工する三つの理由があります。
一つ目は技術レベルの向上です。
公共工事では法律や条例などの制度変更で手続きや工法などが変化します。それに対応するできる技術力がつきます。
技術者の資格やレベルにより工事範囲が限られてきますので、資格取得や技術向上の意欲が増します。
二つ目は経営の安定です。
建設業は繁忙期と閑散期があり、売上が一年を通して安定していません。
公共工事は5月頃から入札があり、受注後の工期が12月から3月迄が多いですので、約半年間は安定して経営できます。
三つ目は地域からの信用です。
公共工事は経営審査により施工業者が優劣順にA、B、Cの3段階にランク付けされます。
岐阜県建設工事等入札名簿によると建設工事一式(岐阜市に本店)登録業者は78社でAランク企業は44社です。
弊社はAランクで上位33位になります。
Aランク企業は建築一式工事における5,000万円以上の工事を施工できる業者になります。
・2026.1.19岐阜県HP業者一覧はこちら
・格付け資料はこちら
公共工事は会社の経営、財務内容、技術力などを総合的に判断された上で、格付けされた入札案件を入札して落札後に工事を施工できます。
ランクが上がれば信用が高い業者となりますので、それだけ地域社会に貢献できる企業とも言えます。
現在は岐阜市内業者の中で33位になりますが、トップ10位以内を目指し努力していきたいと思います。

令和6年度公共工事 岐阜市発注 大洞団地外壁改修工事 (担当者 内木)

令和6年度公共工事 岐阜市発注 一日市場水防団員詰所新築工事 (担当 平工)

令和6年度公共工事 岐阜市発注 長良東小学校ほか外壁改修工事 (担当 渡邊)
村瀬建築では、より良い住まいとなりますよう、ぎふ県産材ヒノキや無垢材を使用した新築、改築、リフォームやリノベーション、古民家リノベーション、耐震診断・耐震リフォームなどの災害対策、手刻み大工の家づくりなど様々な暮らしづくりのお力になります。お気軽にご相談ください!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
博和会旅行 in 石川
皆様、明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
施工部の内木です。
本日は去年博和会の旅行で石川県に行ってきましたのでそのお話です。
12/6.7の2日間で1日目は能登、2日目は金沢へ行ってきました。
能登は復興の応援に行って以来、約10か月ぶりでした。
1日目はまず七尾のイタリアンレストランでの昼食でした。

昼食のようす
ご飯もおいしかったですけど、個人的には色々なビールが飲めて初めて飲むものしかなくて、ものすごく楽しいランチタイムでした。
次にのとじま水族館へ行きました。
実は2月に一度伺いましたがその時はまだよそへ預けられている魚が多く閑散としていました。
それから10か月後ということでどれだけ変わっているのか、ワクワクしていました。
見違えるぐらい観光客がいっぱいいて魚もたくさん帰ってきていてとても賑わっていました。

ジンベイザメのモモちゃん 元気そうに泳いでいました。
入口入ってすぐの一番大きな水槽もたくさんの魚が元気そうに泳いでいてとてもほっこりしました。
水族館のあとは温泉で疲れを癒しました。

和倉温泉 総湯
能登へ復興に行っていた際とてもお世話になった温泉です。
復興応援に行った時、この近くの宿に泊まらせていただいていたので旅館の方へ挨拶に伺いました。
お変わりなく元気そうにしていました。
自分の事も覚えててくださっていて久しぶりにお話もできて良かったです。
そして、温泉のあとはいよいよ夕食です。
今回の旅行で一番楽しみにしていました。

ちゃか寿し
能登復興に行った際に休みの日社長が何回も連れて行ってくださいました。
お店は七尾湾が目の前で市場も近いため、新鮮なお魚がいただけます。
ここのお寿司を食べたらもうほかのお寿司では満足できません。
取れたての新鮮な魚は本当においしいです。
ちなみに僕のイチオシは海鮮丼です。ここに行く際はぜひ食べてみていただきたいです!
2日目は金沢へ行きました。まずは兼六園でした。
この日は朝から天気が少し悪く、、、途中途中で雨が降ることも多少ありました。
ですが一度行ってみたいと思っていたところだったので今回行くことができて嬉しかったです。
昼食は能登牛をいただきました。

お肉がおいしすぎておもわず白ご飯を食べすぎてしまいました。
昼食後に行った近江町市場の食べ歩きではほとんどなにも入りませんでした。
2日間を通してごはんの話ばかりになりましたが印象に残ってるものが多すぎて今回たくさん紹介しました。
震災から二年。まだまだ復興の手が届いてないところもありますが少しずつよくなっています。
なかなかまだ行きづらいかもしれませんが、ぜひ一度能登を訪れてみていただきたいです。いい場所、おいしいものがたくさんあります。
今回紹介したところ以外のほかの魅力を探してみるのも楽しいと思います!
村瀬建築では、より良い住まいとなりますよう、ぎふ県産材ヒノキや無垢材を使用した新築、改築、リフォームやリノベーション、古民家リノベーション、耐震診断・耐震リフォームなどの災害対策、手刻み大工の家づくりなど、様々な暮らしづくりのお力になります。お気軽にご相談ください!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
岐南工高企業フェア参加
みなさんこんにちは!
新築・改築・リフォーム・リノベーションあなたのこだわりお聞かせください。
村瀬建築㈱ 営業設計部の市川です。
今回は12月15日(月)に県立岐南工業高校にて企業フェアに参加しました。
夏にこの企画の話を岐南工業高校よりお聞きし、準備を経て参加いたしました。

始まる前の準備

土木学科の2年生の方がお話を聞いてくれました。

会の後半にも3名の方がお話を聞きに、立ち寄ってくれました。
ホームページにも掲載しています、kodawari通信を軸に、村瀬建築㈱の150年の歴史や後世に匠の技術を伝える取り組みをしている事などをお話させてもらいました。
kodawari40号は150周年記念号として、村瀬建築の歴史や今後の取り組みが掲載されています。
下記画像をクリックして読んでいただけると幸いです。

今回の企業フェア参加会社は28社岐阜県で建設業を営んでいる企業が集まりました。
岐南工高の土木学科1年生2年生、建築学科1年生2年生を対象とした企業フェアです。
インフルエンザの猛威により、建築学科のクラスは学級閉鎖になり、お話を聞いてもらえませんでしたが、学科関係なく、色々な企業が岐阜にはあるという事を知ってもらうのも、将来につながる一部だと思いますので、高校生の方にとっては企業の話を聞けるのは、良い機会だったと思います。
来年の4月より、岐南工高の卒業生が入社予定です。
休み時間を利用して、村瀬建築のブースまで挨拶に来てくれました。来年の4月からよろしくお願いします。
村瀬建築では、より良い住まいとなりますよう、ぎふ県産材ヒノキや無垢材を使用した新築、改築、リフォームやリノベーション、古民家リノベーション、耐震診断・耐震リフォームなどの災害対策、手刻み大工の家づくりなど様々な暮らしづくりのお力になります。
お気軽にご相談ください!最後までお読みいただき、ありがとうございました。
S様邸路地門柱修繕
みなさんこんにちは!
新築・改築・リフォーム・リノベーションあなたのこだわりお聞かせください。
村瀬建築㈱ 施工部の渡邊です。
今回はS様邸路地門柱修繕工事についてお伝えさせていただきます!
S様は先代からのお客様で、今回は「庭路地の門柱が腐って倒れそうな状態であるため見てほしい」との依頼がありました。

既設路地門柱(全景)

既設路地門柱(根元アップ)

既設路地門柱(根元アップ)
現地を確認すると、根元に銅板が巻いてありましたが、白アリに喰われて芯がほとんどない状態でした。
湿気が多い場所にある木材は、白アリの被害が大きいです。
そこで、白アリ被害に合い芯がほとんどなかった根元部分を切断し、ケヤキ材で補強する方法で修繕させていただきました。

木材加工の様子

木材加工の様子
ケヤキ材をボルトにて接合し、既設の柱に合わせて丸く加工しています。

木材加工の様子
鉋やディスクサンダーを使って、既設の柱に合うように加工していきました。
さらに今回は、束石と門柱をボルトで固定し、束石の周りにコンクリート打設することで、転倒しないよう改修させていただきました。

門柱固定完了の様子

修繕完了(全景)

修繕完了(アップ)
最後にこれからも白アリ被害に合わないよう、防蟻塗料を塗り仕上げました。
また地面に直置きではなく、束石により少しだけ地面より上げたので、白アリも上がってきにくくしました。
村瀬建築では、より良い住まいとなりますよう、ぎふ県産材ヒノキや無垢材を使用した新築、改築、リフォームやリノベーション、古民家リノベーション、耐震診断・耐震リフォームなどの災害対策、手刻み大工の家づくりなど様々な暮らしづくりのお力になります。
お気軽にご相談ください!最後までお読みいただき、ありがとうございました。
村瀬建築150周年式典
お客様、協力業者、社員の皆さんで創業150周年の式典を開催させていただきました。
お客様からのサプライズマジックショーあり、協力業者からの動画演出ありで、皆さんと楽しい時間を過ごせました。
村瀬関次郎が明治8年に大工業を始め150年目を迎える事ができたのも、お客様、協力業者、社員の方々に恵まれ、ご愛顧、ご支援の賜物と心より感謝いたします。
これからも、お客様に満足していただける住まいを造るよう、歴史を重んじ維持発展してまいりますのでよろしくお願いします。






大工技術の練習
皆さんこんにちは、施工部の内木です。
10月も終わりに近づいてきて、それに伴い一気に肌寒くなってまいりました。
夜、お休みになられる際は防寒対策をしっかりして、寒さに負けないようにしていきましょう。
今回は大工育成についてのお話です。
毎月第一週の土曜日の朝試験があり、その日は社長に見ていただいて試験の合否を教えていただきます。
自分は今、ポンチを使った釘打ちをやっています。
ポンチとは、用途によって少し名前が変わります。僕たち大工が使うポンチは「釘打ちポンチ」と呼ばれるものです。
玄のう(金づち)で仕上げると、どうしても最後釘の周りの木がへこんでしまうという問題が発生します。
ポンチを使うと、釘の頭だけを正確に叩けるので、釘の周りに傷をつけることなくきれいに仕上げることができます。
使い方は、釘の頭にポンチの先端を当てポンチの頭を玄のう(金づち)でたたき釘を木材に打ち込みます。
大まかなやり方はわかっているつもりなのですが、玄のう(金づち)からポンチをはさんで釘まで力を一直線に正確に伝えないと、釘は入っていきません。
力づくでやってもなかなか釘が入っていかないので時間がかかります。
自分は、力を一直線に伝える、ということができないので苦戦してます。
そこばかり意識してやると、釘の打ち方の正しいやり方ができず、余計に釘が入っていかないようになってしまいます。

釘打ちポンチ

ポンチを使った釘打ち練習の様子

ポンチを使った釘打ち練習の様子
わかりづらいですが、上の写真はポンチと釘が一直線になってないため、このままでは釘は入っていきません。
次回の試験は11/1です。
次回の試験までにあまり時間はないですが、早く、正確な釘打ちができるように練習に励みます。

床板切り練習中(渡邊)
「打つ」ことができたら、次は「切る」練習に入っていきます。
このように、一つ課題をこなしても次々に課題が出てきますが、一つ一つ正確にできるようになって、少しづつ立派な大工へ近づけるように頑張ります。
村瀬建築(株)では、ぎふの木を使った主に手刻みでの新築・改築工事、リフォーム・リノベーションなど暮らしの様々なご依頼やご相談のお力になります!
気軽にご相談ください!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
家じまい
みなさんこんにちは!
新築・改築・リフォーム・リノベーションあなたのこだわりお聞かせください。
村瀬建築㈱ 設計部の市川です。
今回は【家じまい】についてお話します。
家じまいとは、終活の一部で自分の住んでいる家を処分して新しい家に住み替えたり施設に入ったりすることを指します。
自分たちが亡くなった後に子ども達が処分に困らないようにしたいと考えている人も多く、日本で注目されている「空き家問題」の対処法としても有効です。

空家になり放置期間が長くなると、建物の老朽化が進みます。

家じまいをする理由はいくつかあります。
子どもに迷惑をかけたくない。高齢になり施設に移ることになった。家やお墓の管理などを託す人がいない。
など、ご家庭の事情によって異なりますが、様々なきっかけがあります。家が空き家になった時のトラブル回避で家じまいする人が大半です。
村瀬建築㈱は家じまいについてのご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
今回は家じまいをご紹介しましたが、村瀬建築の主力事業は建築設計施工です。より良い住まいとなりますよう、ぎふ県産材ヒノキや無垢材を使用した新築、改築、リフォームやリノベーション、古民家リノベーション、耐震診断・耐震リフォームなどの災害対策、手刻み大工の家づくり、様々な暮らしづくりのお力になります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
博和会BBQ
みなさんこんにちは!
新築・改築・リフォーム・リノベーションあなたのこだわりお聞かせください。
村瀬建築㈱ 施工部の渡邊です。
今回は先日行いました、博和会BBQの様子をお伝えいたします!
博和会は、村瀬建築でいつも工事をお願いしております、様々な職種の協力会社さんの集まりです。
毎年9月頃に日頃の感謝を込めて、職人さん達も御招きしたBBQ大会を開催し、より良い工事が出来るよう親睦を深めています。
今年は9/19に総勢20名で行いました。

BBQ大会の様子

BBQ大会の様子

BBQ大会の様子
毎年恒例の社長が作る、とんちゃん焼きそばはとても美味しく、職人さんからも好評です!!
今年は、電気屋さんの新入社員の方も手伝ってくれました!

BBQ大会の様子
短い時間ではありましたが、職人さん達と色々な話をしながら楽しい時間を過ごせました。
特に嬉しかったことは、仕事のため時間ギリギリでも駆けつけてくれた職人さん達がいたことです。
博和会をはじめ、村瀬建築に携わる職人さん達は良い方々ばかりで、感謝の思いでいっぱいです。
村瀬建築では、職人さん達と協力して、より良い住まいとなりますよう、ぎふ県産材ヒノキや無垢材を使用した新築、改築、リフォームやリノベーション、古民家リノベーション、耐震診断・耐震リフォームなどの災害対策、手刻み大工の家づくり、様々な暮らしづくりのお力になります。お気軽にご相談ください!
最後までお読みいただきありがとうございました。